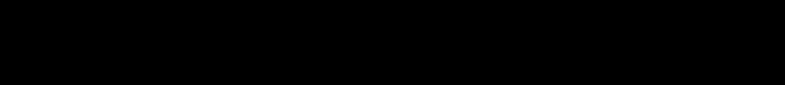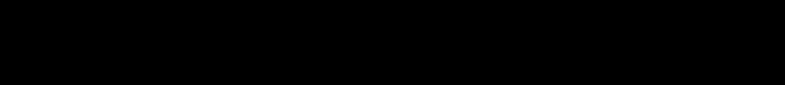|
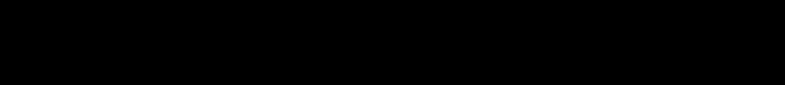
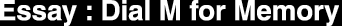

Vol.13 THE MAN WHO IS'T THERE
|

Jun 2002
|
朝、とても眠くて、なかなか眼が覚めない。
なんとかベッドの上に起き上がると、妻も隣で眼を覚ました。
ふと見ると、なんと妻の顔がふたつある。
頭の後ろ側に、もうひとつ顔がついているのだ。
そんなバカな、とあたりを見回すが、いつもと変わらぬ寝室。
よく眼を凝らしても、なにひとつおかしい所がない。
ただ、妻の顔がふたつあって、い ったいどうしたの? と言いたげに、こちらを見ている。
特に怖い顔などではなく、ふつうの妻の表情だ。
あたりを見てもはっきりした現実感があったが、これは夢に違いない、と想った。
そこで眼鏡を外して傍らに置くと、自分の顔を思いっきりひっぱたいた。
二度、三度と強く叩いたが、やはり痛くない。
ああ、やっぱり夢だ。
どうしたらこの夢から抜け出せるのか。
待てよ、こんなに意識も明確で、現実感のある夢(色も音もはっきりしている)は珍しいから、このチャンスを利用してやろう。
夢の中で物事がどうなっているのか、いろいろ調べてみたいという衝動にかられた。
そこでまず外に出ようと寝室のドアを開けた。
とたんに夢から覚めてしまった。
それでも眠くて、なかなかベッドから起き上がれない。
隣では、夢の中と同様、妻が起きている。
いまみた夢の話をすると、「違うところで起きちゃったのね」と微笑んだ。
顔はひとつだった。
違うところ?
これまでの数か月、時間について考え続けてきた。
そして時間はひとつではなく、たくさんあるということが、何となくわかってきた。
だけど今いる自分は、はたしてホントに自分の時間の中に生きているのか。
最近、自信がない。
もしかすると、間違った時間 -間違うという表現が適切でないなら、ちょっとずれた 時間に生きているのではないだろうか。
自分の存在の特殊性については今さら自覚するまでもない。
そもそも生まれが…
というか親が特殊なのだ。
育ち方もたぶん特殊。
その結果、ぼくはどこにも属していない。
事実だけ見れば、とりあえず日本人ではある。
髪は黒くないけど…。
なんか、もうずっと髪を脱色しているので、このままで落ち着いてしまった。
もともと髪が白かったみたいに。
なぜ白髪でもそんなにオカシクないかというと、肌がふつうの日本人より白いんですよ。女性より色、白い。
日本人てやっぱり黄色味がかっているものですが、ぼくはどちらかといえばピンク。
だからホントに純粋な日本人か、と訪ねられると、日本語しか話せないということでしか事実を確かめようがない。
それで自分の会社に所属しているのですが、あまり会社員らしくはない。
一応、代表取締役なのだけれど、社長らしくもない。
一般的なシャチョーのように、ゴルフに行ったりカラオケ・バーに行ったりしないし、 経済のハナシにもあまり興味がなく、お得意先もなく、銀行との付き合いも希薄だ。
そもそも、そんなビジネスの世界は自分と無縁のように感じている。
せいぜい社長らしい仕事と言えば、書類に眼を通してハンコを押すだけ。
だから社長であるというより、社長ということになっている、という感じ。
もうひとつ明白な立場は、手塚家に所属しているということだろう。
しかし、それさえも最近、疑わしい。
某新聞社主催で「手塚治虫文化賞」という漫画の賞があって(実はその名前はぼくが考 えた)、毎年受賞式とパーティが行われる。
ぼくはポリシーとして審査員はやらないから、直接関わってはいないけれど、当然のよ うに招待されて、そこへ行きました。
招待された出席者は全員名札をつけることになっていたが、受付に行くとぼくの名札は存在していなかった。
どこにもなかったのだ。
たぶん、ほんのちょっとしたミスだと想う。どこにでもある手違いなのだろう。
でも、そのとき、ふと想った。
やっぱり、ここにも属していないのか、と。
コーエン兄弟の『バーバー』の原題は"THE MAN WHO WAS'T THERE"。
映画の内容とは別に、いい題名だと思った。
そこにいなかった男。
じゃあ、どこにいたのか。
ぼくは自分では映画人だと想っていて、でもそれはたんに"映画に生きるヒト"って意 味で、映画業界人ってことではない。
学生のころから映画を作っているけれど、そのころは映画業界がキライで、というより なんかノリが合わなかった。
いろいろなプロデューサーと会ったり話したりしたのだけれど、お互い言葉が通じなか った。
ぼくが若かったせいかもしれないが、彼らのハナシは、さっぱり理解できなかったのだ。
ぼくは、ただ面白い映画を一生懸命作ればいいと想っていた。
彼らの話はそんなところから出発しない。
どうすれば儲かるか。お客を呼ぶためにはどんな企画を考えるべきか。どうすればより 宣伝できるか。
何がウケるか、流行がどうのこうの。
映画の内容を面白くするにはどうするか、そんなことを真剣に考えるプロデューサーに は、会った試しがない。
それでぼくは業界を嫌って、映画監督とはいわず、ヴィジュアリストになった。
それから20年。
時代は変わり、業界内では世代も変わった。
同じ学生映画を作っていた同世代の人たちや、もっと若い人たちも、映画会社でプロデ ューサーをやっている。
そこに企画を持ってゆくのだが、やっぱり彼らのハナシは、いまだに謎だ。
どんな面白い映画を作るか、というハナシはなかなか出てこない。
マーケティング的に正しいか、否か。
原作が漫画か、もしくは売れているか。
宣伝に有利な条件があるのか、どうか。
テレビ局や代理店がついているかどうか。
みんなが知っているスターが出ているかどうか。
そんなハナシを散々したあげく、最後には決まって何か新しさが欲しい、という。
ヒッチコックのような映画はどうですか?とぼくが提案すると、古い、と言われる。
古い?
面白い映画が古い?
ぼくも齢を経て、多少の道理はわかってきた。
だから『白痴』や『実験映画』のように意欲的すぎる内容の映画は、映画会社にふさわ しくないぐらいのことはわかっている。
映画会社のプロデューサーと話す時は、そうではなくて、面白い映画について話したいと想っているのだけど…。
みんな「『白痴』みたいな映画は必要かもしれないけど、できませんね」という。
当たり前だ。
ぼくでもそう想う。
だけど「ヒッチコックのような映画は如何ですか?」といって、首を傾げられるのは、理解できない。
「ヒッチコックの映画は大スターが出ていた」
「ヒッチコックの映画は優れた原作があった」
「ヒッチコックの映画はお金がかかっていた」
そうかもしれない。
でも大スターが出ているから、原作が売れたからヒッチコックの映画が面白かったわけ じゃないと想う。
もしかすると、プロデューサーたちは、ヒッチコックの映画というものを知らないか、
さもなければなぜそれが面白いか、わかっていないんじゃないだろうか、と疑いたくもなる。
古典的な映画ではなく、もっと意欲的な映画をやりたい、という果敢なプロデューサー もいないわけではない。
そういう企画は、(ぼくがやってきたほとんどの映画がそうであるように)インディーズ という形態を取らざるを得ない。
ところが呆れたことに、映画会社の人が「インディーズ・シネマを作りたい」という。
インディーズという映画のスタイルがあり、それがいい、という。
でもインディーズというのは、スタイルではないよ。
しかも人気のあるスターが必要だという。
その発想は、もはやまったくインディーズではない。
スターを使わず、自分達の映画を自分達のやり方で作るという意志が、インディーズだ。
わかってない人たちにケチをつけられるのは苦痛だが、世界中の映画監督は、誰だって同じ眼に遭っているのだろう。
やっぱり、ぼくは映画業界は苦手だ。
理解ができないから。
きっと、彼らもぼくが理解できないのだと想う。
映画業界の人たちは、ぼくのことをよく知らない。
ビデオやCMを専門にやっている人間、ぐらいに想っている。
でもビデオやデジタルの業界では、ぼくは映画をやっている、と想われている。
CM業界では、手塚はCMなんか撮らないだろう、と勝手に想われている。
だからCM演出の依頼はまったく来ない。
やりたいのに!
漫画やアニメをやっている、と想っている人々もいる。
漫画やアニメの業界では、実写の監督だと想っている。
けっきょく、どこにも属していない。
ぼくは、そこにいないのだ。
ヴィジュアリストだからではない。
もとから、生まれながらにして、そこにいないのだ。
業界の中でアウトローだということはわかっているのだが、それどころか、社会の中で も、日常の中でも、存在を脇に外されている。
そして、たまにはパンダみたいに珍しがられて、テレビやイベントに呼び出される。
でもそれを"孤独"だの"疎外感"だのというつもりはない。
孤独はいい、まだそこに存在するのだから。
そこにいないのだ。
ムカシからよく、浮いていると言われてきた。
はめ込まれているように、見える。
合成されたCGキャラクターのように。
『スターウォーズ』に登場するエイリアンみたいに、どんなに活躍したって、本来はそこにいない。(やっぱりジャー・ジャー・ビンクスは煩い。邪魔だ!)
本当は別の時間に生きているのかもしれない。
どこかわからないが、ほんのわずか、こことは違う時間。
いまさら、もとの時間に戻りたいとは想わない。
ここでの自分の特殊な存在性を、できるだけ楽しもうと想っている。
人に顔がひとつしかない、この世界の中で、物事がどのようになっているのか、興味を 持って…。
サテ、6月の時点で観に行った映画は50本を超えました。
よしよし。
目標の年間100本に向かってるぞ。
今月のマイ話題作。
『エピソード2』は、やっぱりクリストファ・リーに尽きる。
『ロード・オブ・ザ・リング』でも凄みあったし。
なんたって子供時代のヒーロー、ドラキュラ伯爵その人だもの。
だからといって役名が"ドゥーク伯爵"じゃ、やりすぎか。
そういえば『エピソード1』のとき、まるでエキストラの如く、ちらり出演していたテレンス・スタンプが今回は悪役として再登場か、と思いきや姿も見せなかった。
どういうこと?
次回作には出るの?
もっとオタッキーな発言をすれば、マイ・フェバリット・ムービーである『ヘルハウス』 のバレット博士役のクライブ・レベルは、たしか『帝国の逆襲』でエンペラーの声を演じていた。
のに、その後、一切出演していない。
おいおいルーカス、イギリスの俳優を何だと思ってるんだ?
(でなければ、イギリスの俳優はルーカスをどう思っているか、だ)
どんなにスゴイCGを見せつけられても、結局は俳優の魅力に尽きるのが映画。
で、今月は何が印象に残ったかというと、実は『愛しのローズマリー』だったりする。
グウィネス・パルトロウの体重が120キロという無理やりな設定は、聞くより観るほうが断然オモシロイ。
画面に映っているものを否定して、別の姿を想像しながら観なければならない。
かなりいじわるな演出だけど、視覚についてマジに考えさせられることがいっぱい。
ヴィジュアリストにとって、ホントに興味深い。
とても感心したのは、主人公が遊んだ子供に再会する場面。
主人公の表情と観客の想像力だけで、おかしい、切ない、コワイ、そして胸がキュッと なるような、いろんな感情が浮かんでくる。
まれにみる、秀越な場面になりかけていた。
"なりかけていた"というのは、惜しくもそこで子供の素顔を見せてしまったことで、これはまあ、観客へのサービス・ショットなのだけれど、個人的には最後まで見せないままが良かったかな。
と書いても、観ていないことには何のことかわからないですよね。
スミマセン。
ネタは明かせないので、詳しく説明できないのだけれど。
まあ、おバカな映画ではあります。
ファレリー兄弟の映画は、みんなスキ。
『ジム・キャリーはMr.ダマー』(最高!)『メリーに首ったけ』(もちろん!)『ふた りの男とひとりの女』(かなり)…。
下劣でいじわるな笑いを裏で支えているのは、とてもハートフルな性格と、ハリウッドの健全な娯楽映画感性。
だから、たとえば映画の冒頭、映画会社のタイトルの出し方ひとつでも、「この人たちは 信用できる」って想っちゃう。
さて、信用できないデビッド・ボウイの、新譜。
なかなかいい曲もあった。
信用できないけれど、ボウイは嫌いじゃない。
ぼくにとってのボウイは、残念ながらジギー・スターダストでも『戦場のメリー・クリ スマス』でもなくて、『地球に落ちてきた男』。
『ハンガー』のヨボヨボ・ボウイも捨てがたいけれど。
今回も『光る眼』みたいなジャケット・アートが印象的なのだけれど、なんか見たことある。
と想ったら先月紹介したジョン・フォックスのジャケット・ワークにあまりにそっくり。特に中ジャケの写真。
さすがパクリの天才、ボウイ。
やっぱり信用できないところが、イイ。
こぼれネタとして、ジム・フィータスが新譜を出しました。
(STEROID MAXIMUMS名義)
まるで映画音楽のような、インスト集。
でも、ただのラウンジになっていないところは、さすがにパンク・ノイズ・ミュージシ ャン。
今月もディープなネタばかりになりました。
でも6月だから。
"6"って一番好きな数字なんですよ。
って理由になってないか。
|
|