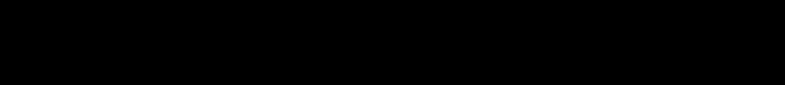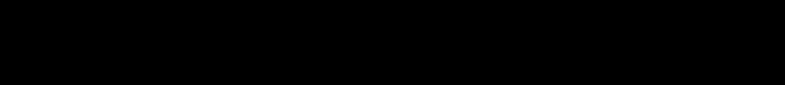|
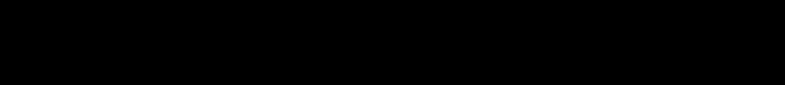
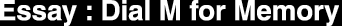

vol.39 30th ANNIVERSARY
|

Jan 2009
|
昨年10月で、ぼくは映画監督デビューから30年になりました。
1978年に、初めて映画を監督したのです。
といっても8mmの高校生映画ですけどね。
それでも友人の中には、いまだに「あの映画が最高だった」といってくれるヒトもいて、嬉しいような、悔しいような。
なにしろその1本がなかったらいまのぼくはなかったかもしれない、というほど鮮烈なデビューで、
高校生の映画コンテストで特別賞を受賞し、審査員の大島渚監督から激賞され、ぴあで上映され、多くの映画人から評価され、
ついには(恐れ多くも)小津安二郎監督の作品と一緒に文化イベントで上映されてしまうという事態まで起こり、
まったく本人の予想もつかぬ反響で、慌てました。
なんて書くと「見たい」といわれそうなので、さすがにもう恥ずかしい、なにしろ高校生が初めて作った映画ですよ。
ヘタクソを絵に描いたとはまさにこのことで、恐らく他の高校生よりほんの少しだけ“マシ”だった、という程度だったと思います。
だからいまは封印して、もう数十年、陽の目を見ていない。(DVDなんてとんでもない、ビデオにすらなっていない、8mmフィルムのまま)
ただ、作家はいずれデビュー作に帰ると言われてますね。
初心には少なからずそのヒトの本質がシンプルに示されているものです。
作家のロアルド・ダールは「人生のカードには1つの手しかない」というようなことを書いていたそうですが、
処女作には生涯変わらぬテーマが潜んでいるのかもしれません。
その映画の題名は『FANTASTIC★PARTY』で、テーマは・・・
テーマは、「青春はいつでもファンタスティックなパーティである」でした。
いまなら「人生はいつでもファンタスティックなパーティ」だと言うところでしょう。
30年間を振り返ってみました。
色々ありました。
父親を亡くしたり、結婚をしたりもしました。
辛いこと、いっぱいあったかもしれません。嬉しかったことも負けずにありました。
そしていま想うことは、やぱりそれはすべて「ファンタスティックなパーティ」だったな、と。
いつも楽しかった、という意味ではありません。
いつもタイヘンでした。お祭り騒ぎなんです。サーカスのようです。綱渡りなんです。
ですが、当事者であるにもかかわらず、それを傍観して面白がっている自分がいます。
だからすべての瞬間が「ファンタスティックなパーティ」に映るんですね。
ぼくは自分の人生を、いまでもヴィジュアリストの生活、なんて言って、なんだか寓話のように、SFのように、夢と同じように慈しんでいます。
1990年に書いた「ヴィジュアリスト宣言」の中に、こんな一文がありました。
ヴィジュアリストは、そう、楽しんで生きている。
欲でも、権利でも、思想でも、条件でもなく、生きるものの基本的な原則に従って、楽しく生きている。
明日死んでしまうとして、でもそれが何だというのだろう。今日のヴィジュアリストは生命の向くまま、世界のあらゆるナンセンスの中で踊る。
ワクワクしながら人生を過ごす。
「君は甘い」と云われるならば、想いっきりチョコレートにくるまれてみせる。
「君は子供」と云われるならば、二百歳まで生きてみせる。
ぼくは地球に、ぼくの夢をみさせてみたいのだから。
30年の間に、あらゆる表現に手を染めました。
映画だけではなく、テレビもネットも、小説もイベントも、マンガもアニメも・・・。
なんでそうなってしまったのか、なんて疑問はありません。とはいえ、スキ好んであらゆるものに手を出したわけでもないんです。
自然にやってしまっていたのです。
ただ、それを否定しない自分がいただけなんです。
成功したものも、失敗したものもありました。楽しかったものも、ただ辛かったものも、なんだかわからなかったものも。
みんなひっくるめて、「よくやってきた、節操なく」と想えるんですね。
そしてこのパーティは終わらない。
何時までも、いつまでも。
「人生が常にファンタスティックなパーティならば、それは永遠の青春である」
|
|